脳卒中後、自主トレを続ける3つのコツ!!
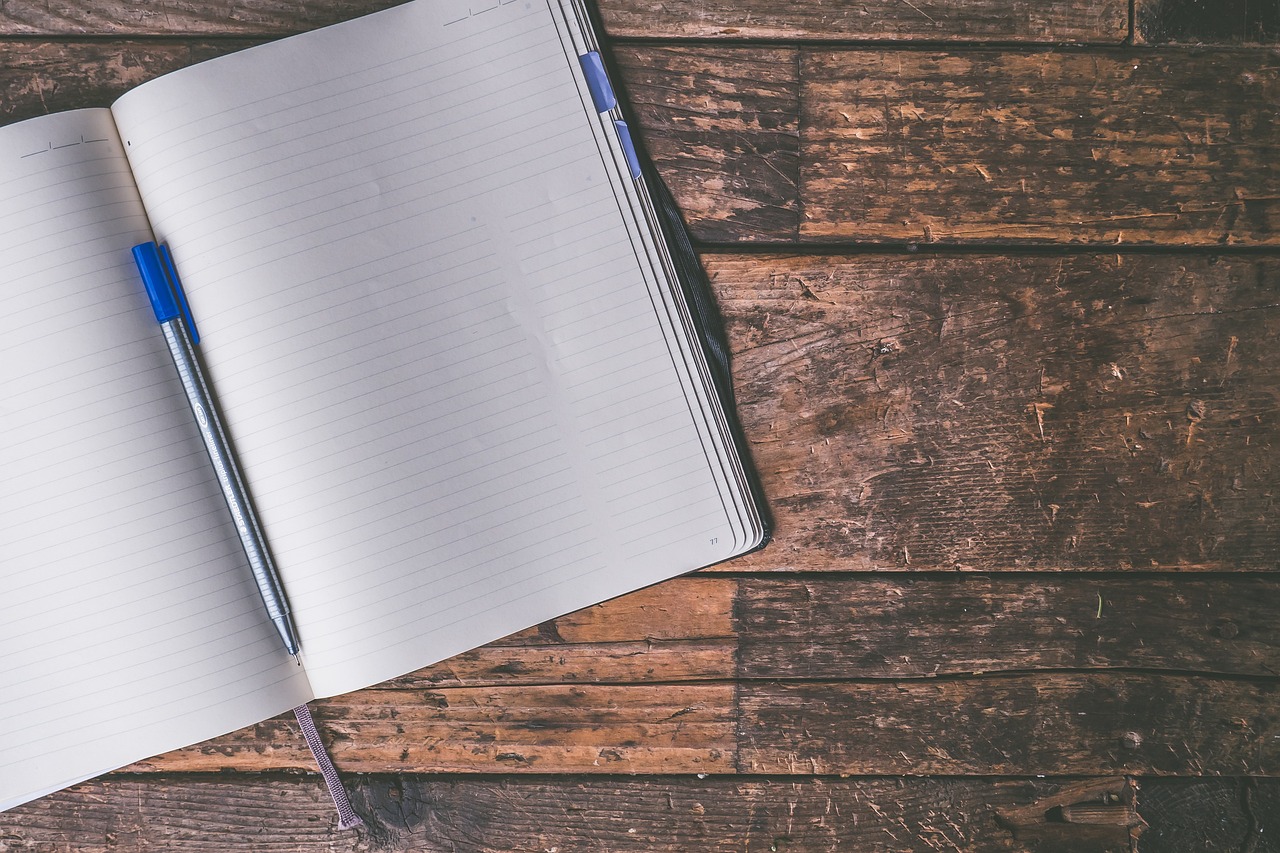
はじめに
脳梗塞や脳出血の後の後遺症には、運動麻痺(手足に思うように力が入らない)、痙縮(力が常に入ってしまう、歩くだけ手にも力が入ってしまう)、感覚障害(触れている感じ、関節の動いている感じがわかりにくい)や高次脳機能障害などさまざまな症状が残存することがあります。
リハビリはこれらの症状の改善に有効ですが、入院中に比べ退院するとリハビリの頻度や量が減少してしまいます。入院中もそうですが、退院後は特にセラピストとのリハビリに加えてご自身による自主練習によるリハビリも重要になります。
脳の可塑性(損傷してしまった場所を他の場所が補うように変化する反応)を促すには麻痺した手足を動かす、手足に感覚を与える、自分の意識を麻痺した手足に向ける
これらの刺激をなるべく多く入れることが重要です。麻痺した手足は意識しないと1日中なんの刺激がない状態にもなりかねません。
これから自主トレを続ける重要性や続けるコツについてご紹介していきます。
自主トレーニングの重要性
家でのリハビリは、次のような理由でとても重要です。
▶ 続けることで脳を刺激し脳の可塑性を促す
▶ 生活習慣の中に麻痺側の手足を使った運動や動作を取り入れることで麻痺側を使う頻度を増やせる。そのため運動学習(脳が運動を学習する機能)が促進されやすい。
▶ 自宅という安定した環境で、続けやすい
病院やリハビリ施設では1日数時間のリハビリでも、自宅生活は24時間続きます。日常生活の中の動作で補助でも、少し動かすだけでも週に何回かのリハビリよりも多くの回数、時間を動かすことができます。この機会を逃すのはもったいないです。
しかし注意点があります、誤った手足の使い方を続けると誤学習と言って悪い形で運動学習が進み痛みなどに繋がってしまう可能性があります。新しい自主トレを始める時はリハビリを受けているセラピストなどに相談することをお勧めします。
続けるための3つのコツ
◆ 目標を「小さく」「コンパクト」に

大きすぎる目標は、すぐに挫折してしまい自主練習をやめてしまう原因になりやすいです。
例:「1日に1回、左手でコップを持つ」
「まっすぐ立つ時に、左足を意識する」
身体の状態はそれぞれ違いますので目標設定は難易度や環境などさまざま調節する必要があります。セラピストに相談していただき一緒に決めていくことでリハビリの内容もその目標に沿うものに近づきやすいです。
◆ 「楽しい」を大切に

リハビリと聞くと、どうしても「つらい」「きつい」というイメージが先行します。
しかし、本来、からだを動かすことは楽しいことです。
例:「女性ならバランスボールを使って気分よく」
「歌を聞きながら手足を動かす」
「子供さん、お孫さんとゲーム形式で」
「今日は何回できた!!と記録をつける」
◆ 人との繋がりを生かす
ひとりきりで続けるのは難しいもの。
例:「今日はこんな動きをしたよ!」とご家族に報告
「セラピストに練習を頑張ったことを報告」
セラピストや家族とコミュニケーションを受けることで、続ける助けになります。
おわりに
自主トレで大切なのは、「自分を認め、褒めて、大切にする」ことです。
「まだよくならない」と気を落とすのではなく、「今日も頑張った自分」を褒めること
続けることで、必ず「あの時頑張ってよかった」と思える日がきます。
私たちセラピストも、みなさんのそれぞれの歩みを心から応援しています。
疑問や不安な点があれば、気軽にご相談ください。
川平法やHAL®を体験してみたい方!
無料体験はコチラ
LINEの友だち登録をしていただくと、お役立ち情報の配信をお知らせします!
LINEの友だち登録はコチラ
また、改善事例や動画もたくさん公開していますのでご覧ください!
改善事例・動画はコチラ

この記事を書いた人
令和2年に理学療法士国家資格を習得。同年から令和6年12月まで群馬県玉村町にある医療法人樹心会角田病院、介護老人保健施設たまむらで勤務し、回復期リハビリテーション病棟、老健通所リハビリを経験しながら、主に脳梗塞、脳出血・脊髄損傷・骨折・神経難病の患者様のリハビリに携わる。その間に神経領域の学術大会・研修会に参加し、神経疾患に対するリハビリを中心に学ぶ。令和7年1月からリハビリスタジオ群馬に勤務。
